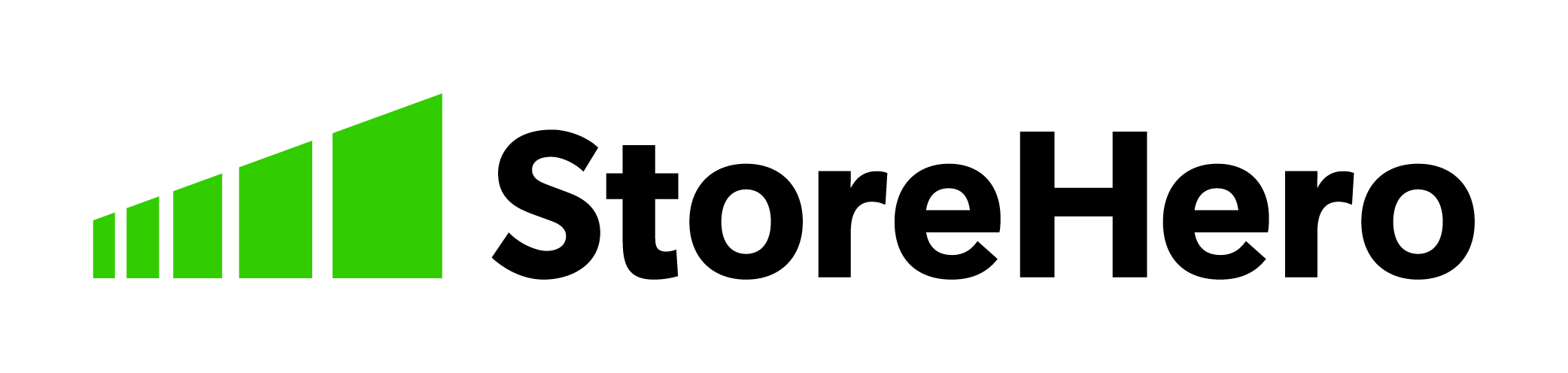Contents
アルビオン×チャネルトーク×StoreHeroが語るECの未来
EC市場が成熟し、モノが溢れる現代。顧客は単なる「商品」ではなく、「楽しい買い物体験」を求めています。しかし、その「楽しさ」とは一体何なのか? どうすればオンラインで、あるいは店舗と連携して実現できるのでしょうか?
今回は、化粧品メーカーの「アルビオン」、チャット接客ツールで顧客コミュニケーションをデザインする「チャネルトーク」、Shopifyを活用したグロース支援を行う「StoreHero」の3社が集結。「買い物の体験を楽しんでもらう」をテーマに、AIと人の最適な関係から、顧客の感情曲線、未来の買い物像まで、徹底討論しました。
登壇者紹介
株式会社アルビオン
国際ブランド営業部 国内推販グループ グループ長
榊原 隆之 氏

【略歴】
1990年株式会社アルビオン入社。全国の有名化粧品店、百貨店への卸営業を20年務めた後に、ライセンスブランドの国内外マーケティングや営業を管轄する国際事業本部に着任し、現在はANNASUI、PAUL & JOEの国内展開を担当している。2019年から自社オンラインストアの開設、運営も担当し4ブランドのオンラインストアサイトを立ち上げてきた。
株式会社 Channel Corporation
執行役員・VP of Operations
鈴木 諒氏

【略歴】
2016年、株式会社ベーシックに入社し人事として採用・育成・評価制度を担当。
2021年、外資系AI企業Channel Corporationに入社。CS・営業・マーケ・採用・事業開発を
経て執行役員に就任。
2025年よりVP of Operations。4部門を統括し、日本リージョンの利益最大化を推進。
株式会社StoreHero
Co-founder & 代表取締役CEO
黒瀬 淳一

【略歴】
筑波大学卒業、神戸大学大学院修了後、(株)アクシイズに参画。
取締役としてSaaSの開発/販売に従事し、同社を売却。その後、(株)インターネットインフィニティ、(株)チームスピリットに参画し、事業開発、営業/マーケティングを担当し、その後、同社はそれそれ上場。Ginzamarkets(株)のカントリーマネージャーを経て2019年、(株)StoreHeroを創業。
買い物の「マインド曲線」とは? 楽しさの第一歩は「上げない」より「下げない」工夫
黒瀬: 本日は「買い物の体験を楽しんでもらう」をテーマにお集まりいただきました。この話題のきっかけとして、ぜひ榊原さんに伺いたいのが、榊原さんが提唱されている「買い物マインド曲線」という考え方です。これはどういうものなのか、まずご説明いただけますか?
榊原氏: はい。コンビニで日常品を買うのとは違い、ファッションや嗜好品などの買い物には、お客様の感情の浮き沈みがあります。これを「マインド曲線」と呼んでいます。
例えば、お店に入った瞬間に「汚い」「臭い」と感じたら、感情は急降下しますよね。よく「良いものを提供する」ことで感情を「上げる」イメージがありますが、私は「下げない」工夫も重要だと考えています。
黒瀬: 「下げない」工夫、ですか。
榊原氏: そうです。例えば、良いものが見つかったのに、レジでポイントカードの勧誘をされて20分も待たされたら、せっかくの満足度が下がってしまいます。家に帰って商品を開けた時に「ありがとう」というメッセージが入っていたら、気持ちはぐっと上がります。
不満がない状態を作ることと、気持ちが上がるポイントを作ることが大切です。オンラインでもこの曲線は意識できるはずですが、店舗とはまた工夫の仕方が違いますよね。

AI vs 人間? 顧客が本当に求める接客の「最適解」
黒瀬: 鈴木さん、チャネルトークさんではチャット接客で買い物の楽しさを支援されていますが、最近主流になってきているAI接客と、従来の人の接客との最適なバランスについて、ぜひお話を伺いたいと思います。
鈴木氏: 買い物の楽しさという点で「AIと人の最適なバランス」についてよく聞かれますが、正直、最適な「バランス」はないと思っています。一番大事なのは、お客様自身が「選べる状況」にあることです。AIだけで対応するのも良くないし、人だけで問い合わせが溜まって返信が遅くなるのも良くない。
AIには欲しい情報をスピーディに提供する役割を持たせ、人にはAIでは回答できないような、感情に寄り添う回答をできるだけ早く提供する。この両方の選択肢を準備しておくことが重要です。
傾向として、男性はAIで早く答えが欲しい、女性は会話をしながら背中を押してほしい、といった違いもあります。チャネルトークでは、あえてAIと有人の窓口を並べて表示する実験をしたことがあります。当初は会話(有人)を重視していましたが、意外にもAIを選ぶ人が多く、「早く答えが欲しい」というニーズが明確になりました。
どちらも選べるという「安心感」が大事なんです。ただ、「秋の気配を感じる」といった言語化しにくい、感情的な部分を共有・共感できるのは、やはり人間の強みですね。
オンラインとオフラインの「境界」をあえて設けない体験価値
黒瀬: 今、店舗(オフライン)の話が出ましたが、榊原さんにお伺いします。アルビオンさんでは、オンラインとオフラインをどのように連携させて「楽しさ」を作っていますか? オンラインだけではできない体験もあるかと思います。
榊原氏: 私たちは、オンラインとオフライン(店舗)について、あえて「統合」も「差別化」もしていません。
もちろん、オンラインだけでできないこと、店舗だからこそできることはあります。ですが、それらを無理に融合させたり、逆に厳密に区別したりすることはしていないんです。
お客様が、その日の気分で自由に選べることを大切にしています。今日は店舗で直接相談しながら買いたい気分かもしれないし、明日はオンラインで手軽に買いたい気分かもしれない。
重要なのは、お客様がどちらのチャネルを選んだとしても、そのチャネルでできる限りの「最善(最適)の体験」を提供することだと考えています。それぞれのチャネルの特徴を活かしつつ、お客様の期待に応えていく。その積み重ねが楽しさに繋がると考えています。
鈴木氏: その視点は非常に重要ですね。私たち(チャネルトーク)も、オンライン上で「店舗のような当たり前の体験」を提供することを目指しています。
例えば、店舗なら、お客様が商品棚でずっと悩んでいたら「何かお探しですか?」と声をかけますよね。これは当たり前の光景です。しかし、なぜかECになった途端、問い合わせ窓口をページの隅に置いて、あとはご自由にどうぞ、という形になりがちです。
チャネルトークでは、店舗での「能動的な声かけ」をオンラインで実現できます。特定のページで1分滞在して悩んでいるお客様に「何かお困りですか?」とポップアップで話しかける。これはまさに、オフラインの接客体験をオンラインに持ち込む試みです。
黒瀬: なるほど。オフラインでの顧客体験が、オンライン施策のヒントになるわけですね。
榊原氏: そうですね。お客様の体験をチャネルで分断するのではなく、それぞれの良いところを活かし、お客様の行動や感情を深く理解することが、結果としてオンライン・オフラインの垣根を越えた「楽しさ」に繋がっていくのだと思います。
データと「勘」で見極める顧客の“楽しさ”
榊原氏: 私から聞いてみたいのが、オンライン上の「楽しさ」をどう可視化するか、という点です。黒瀬さんは、データ上で顧客の「楽しさ」をどう分析されていますか?
黒瀬: そうですね、感情そのものは分かりづらいので、結局は「行動」でしか捉えられません。ただ、例えば「いっぱい買っている」からといって、必ずしも「楽しい」かどうかは分からないと思っています。
購入金額で見ることも多いですが、それだけでは判断できません。私が注目しているのは、買う・買わないに関わらず「よくウェブサイトに来てくれる」とか「イベントのたびに必ず参加してくれる」といった行動です。用事がなくても来てくれるというのは、楽しみに来てくれている証拠ですよね。
榊原氏: 確かに、訪問回数(頻度)は重要ですね。
滞在時間もよく見られる指標ですが、ただ伸びているだけだと、サイト内で迷っている(ストレスを感じている)可能性もあり、危ないかなと思います。ブランド体験のために用意したコンテンツをしっかり楽しもうとしてくれている動きが見えた上で滞在時間が長いのであれば、それは良い体験だと判断できます。
黒瀬: なるほど。データと、その背景にある「勘」や文脈の読み取りがセットで必要だということですね。鈴木さんはそのあたり、どうお考えですか?
鈴木氏: まさにデータと勘の組み合わせですね。チャネルトークでは会員情報と連携できるので、お客様がチャットに来るまでに「10個の商品ページを見ている」というデータが分かると、「この人は相当悩んでいるな」という「勘」が働きます。
そこで、その10個のデータに基づいた個別提案ができる。これが「個別化(パーソナライズ)」です。やりすぎると「なんで知ってるの?」と気持ち悪がられますが、「私のこと分かってくれてる」と感じてもらえるバランスが重要です。
能動的な「声かけ」が安心感とLTVを生む
鈴木氏: もう一つ大事なのが、問い合わせを待つ「受け身」ではなく、「能動的なアクション(声かけ)」です。
店舗なら、お客様が商品棚でずっと悩んでいたら「何かお探しですか?」と声をかけますよね。ECだと、なぜかそれがありません。チャネルトークでは、特定のページに1分滞在したら「お困りですか?」とポップアップで声をかける機能があります。
面白いのが、この声かけによって必ずしもチャットが増えなくても、コンバージョンが上がった事例があることです。これは「いつでも聞ける」という「安心感」が購入を後押ししたのではないかと推測しています。
黒瀬:その声かけは、LTV(顧客生涯価値)にも繋がりそうですね。
鈴木氏: 実は、ある企業でチャット接客を導入した際、既存顧客のLTVはあまり変わらなかったのですが、新規顧客の1年後LTVに、有人接客の「あり」と「なし」で驚くほどの差が出たんです。
接客を受けた人の方が、明らかに顧客ランクが高くなっていました。これは、ただ商品を買う(点)だけでなく、「悩んで、相談して、決めた」というコミュニケーションが「思い出(体験)」になっているから。この体験は、他のブランドでは代替できない価値になります。

買い物の頂点は「決めた!」瞬間。決済はストレスフリーに
黒瀬: 顧客の感情という点で言うと、榊原さんのマインド曲線の「頂点」はどこに来るのか気になります。
榊原氏: 以前アンケートを取ったことがあるのですが、お客様のテンションが一番上がるのは「選んでる時」や「悩んで、比較して、ついに『これに決めます!』と覚悟が決まった瞬間」や「商品が届いて開封する時」だという結果が出ました。
鈴木氏: 分かります。僕らが店舗スタッフにヒアリングする際、「お客様のテンションが上がる時」を調べてもらいますが、それがまさに「会話(接客)をしている時」なんです。「悩んで、比較して、決まった時」が頂点なんですね。
黒瀬氏:なるほど、接客中も頂点なんですね。
榊原氏: 「相談する」「悩む」というプロセス自体も、気持ちが上がっていく重要な体験ですね。 一方で、私が注目しているのが決済の瞬間です。ここはお金を払う行為で、せっかく上がった気持ちがスッと下がってしまう(なくなる)危険なポイントです。 特に初めてのお客様だと、「会員登録してますか?」「ポイントカード持ってますか?」と何度も同じようなことを聞かれ、やっと登録が終わったと思ったら……と、ストレスがかかりやすい。 この「頂点」まで上がった気持ちを下げないためにも、決済体験は徹底的にスムーズに、ストレスなく終えられる設計が重要だと考えています
顧客の声は「聞きに行く」。ネガティブフィードバックこそ改善の種
黒瀬: では、次のお題に移ります。接客をしていると、店舗でもオンラインでも様々なお客様の声が集まってくると思います。こうした「顧客の声」を、サービス改善や、それこそ「楽しさ」を作るためにどう活かしていくか。この点はいかがでしょうか? 榊原さん、まずお願いします。
榊原氏: 例えば店舗だと、接客に対するお客様からのネガティブなフィードバックは、スタッフもすごく落ち込んでしまうんです。「あのスタッフの接客は良くなかった」という声がお店に伝わると、やはり人間なので…。
その点、オンラインは(人の感情を介さない分)お客様の声を素直に反映させやすい側面はありますね。サイトのUI/UXなど、システムの改修で対応できることも多いですし、お客様側も自分で色々試しながら最適な使い方を見つけてくれることもあります。
黒瀬: 確かに、オンラインの方が改善のサイクルは回しやすいかもしれませんね。鈴木さんはいかがですか?
鈴木氏: 顧客の声という点では、僕らは「能動的にフィードバックを収集する」ことを推奨しています。
ある企業では、①チャット接客直後の「チャット評価」と、②購入7日後の「買い物全体の評価」を自動で送るようにしました。
すると、②のフィードバックで「商品は良かったけど、梱包がダサかった」という声が見つかったんです。これは、受け身で問い合わせを待っているだけでは絶対に気づけません。すぐに梱包デザインを変更したところ、今度はSNSで「梱包がおしゃれ」という投稿が増えるようになりました。
チャット接客のレビューも、担当者ごとに履歴と評価が紐づくので、振り返りが可能です。うちのチームでは、5段階評価で「1」か「2」(ネガティブ)がついたら、全員に通知が飛ぶようにしています。それは「ダメだ」と責めるためではなく、「まだ解決していないことがあるのでは?」とチーム全員で即座にカバーしに行くためです。
【未来予測】AIエージェントと「スーパーコンシェルジュ」が創る次の買い物体験
黒瀬: それでは最後に、未来の話をしたいと思います。AIの登場でECもさらに進化していくと思いますが、「買い物を楽しむ体験の未来」は、どのようになっていくでしょうか。お二人のご意見をお聞かせください。
榊原氏: 最近、百貨店が昔のようなマス向けの商売から、一人ひとりに担当営業がつくようなパーソナル対応に変わってきていると感じます。
もしかしたらオンラインでも、そういう「スーパーコンシェルジュ」的なAIエージェントができて、個人の好みを完璧に理解した上で、自動でおすすめをカートに入れてくれる、決済をすませてお家に届く。そんな未来が来るかもしれません。今とは全く違うビジネススタイルですが、そういうことも起きるかもしれないと思っています。
鈴木氏: 未来の買い物は二極化すると思います。 一つは、「早く買いたい人」のための体験。AIが好みを推測し、シームレスに、なんなら自動で服が家に届くような形です。 もう一つは、「買い物を楽しみたい人」のための体験。AIが「これもどう?」「こっちも似合うよ」と次々に提案し、気づいたら2〜3時間サイトを見ているような、「選ぶ」こと自体の時間価値を最大化させる仕組みです。
黒瀬: そうなると、人間のスタッフに求められるのは、商品知識だけでなく、他社の商品も含めた幅広い知見や、その人自身の人間的魅力、エンターテイメント性といった部分になりますね。昔のカリスマ店員のように。
鈴木氏: AIか人間か、お客様には判別がつかないレベルになるかもしれません。
黒瀬: 決済体験も、PayPayが登場した時のような革命がもっと起きてほしいですね。
鈴木氏: 金額を「気にさせない」シームレスさが鍵だと思っています。もちろん金額は明示しますが、リアルでSuicaやPayPayで払う時のように、細かい金額を意識させない。それでいて、後で明細を見て「こんなに!?」と怒らない程度の、絶妙な体験設計が重要になってくると思います。

まとめ
「買い物の楽しさ」とは、一つの機能で完結するものではありません。顧客の感情の起伏(マインド曲線)に寄り添い、ストレス要因を徹底的に排除すること。AIと人間の接客を「選べる」安心感を提供すること。そして、データと「勘」を融合させた能動的なコミュニケーションによって、単なる「購入」を「思い出」に変えていくこと。
技術(AI)の進化は、私たち人間の「体験」をより豊かにするためにこそ、使われるべきなのかもしれません。
Shopify×グロース支援のお問い合わせ
StoreHeroでは、Shopify×グロースの専門チームが打ち手を爆増し売上を伸ばすShopify×グロース支援サービスを提供しています。
StoreHeroとShopify×グロースに取り組むことにご興味のある方はお問い合わせください。